|
しかし、ジャアク商会の藤井としては、こういう原稿で誌面を覆い尽くしてみたかったというのが本音。 そんなわけで、一般読者の方からのリクエストが非常に多かった 「ホイアン郡の橋 完全版」 をここで掲載することにしました。お時間のある方はぜひお読みになってください。 |
|
しかし、ジャアク商会の藤井としては、こういう原稿で誌面を覆い尽くしてみたかったというのが本音。 そんなわけで、一般読者の方からのリクエストが非常に多かった 「ホイアン郡の橋 完全版」 をここで掲載することにしました。お時間のある方はぜひお読みになってください。 |
|
ホイアンに屋根付きの橋がある。そう聞いたわたしが頭に思い浮かべたのが小説 『マディソン郡の橋』 である。 そこでホイアンの話に戻るが、とにかく行って見ることにした。表向きの理由は取材だが、裏の理由は当然ながら“偶然を求めて”だ。 その瞬間からキンケイド藤井以外のなにものでもなくなったわたしは、荷物をまとめるとスーパーカブ70にまたがった。本物のキンケイドは古いシヴォレーのピックアップ・トラックに乗っているが、わたしは古いホンダのスーパーカブ。共通点は古さだけだが、なにごともポジティブに考えるわたしには影響なく、ベトナム版フランチェスカの待つホイアンを目指して走りだした。 マディソン郡にある屋根付き橋の名はローズマン・ブリッジという。一方、ホイアンのそれは遠来橋と呼ばれている。 この小説によれば、キンケイドは目指す橋が見つけられず、捜しまわっているうちにフランチェスカと出会い、彼女の家に呼ばれる。夕食には菜食料理が出され、ベジタリアンの二人はすっかり意気投合。その後は二人でダンスを踊り、結ばれる。 「わたし、敬謙な仏教徒だから肉が食べられないの。だから、夕食はコムチャイなんだけど、それでもいいかしら」 などと言い寄ってくる可能性もないことはないのだ。 夕食のコムチャイメニューを思い浮かべながら、わたしはバイクを走らせた。偶然とは不思議なもので、ホイアンに到着したものの、わたしもキンケイド同様に、屋根付きの橋が見つけられない。ホイアンは小さな町だから簡単に見つけられると思っていたのだが、一方通行の標識が多くて混乱してしまうのだ。 彼らのアドバイスを得て、デタラメに市内を走り回っていると港に出た。ガイドブックによればここから橋は近いはずだが、フランチェスカの姿はどこにもない。 「ハロー、ミスター、なにしてるの? バイクを停めるならここよ」 そんなところで地図なんか広げていないで、お店の中で休んでいきなさいと言う彼女は港前の喫茶店で働く給仕らしい。遠目で見るかぎりでは小柄だが、目鼻立ちが整っていて、色白の肌に長い黒髪が似合っている。どこか日本的な面影があるが、この町にはかつて日本人町があったというから、ひょっとするとその末裔かもしれない。 声の主が美女だったので、迷わずバイクを停めて店に入った。港に美女の取り合わせは 『マディソン郡の橋』 ではなく 『ギターを持った渡り鳥』 だろうが、キンケイド藤井は小林旭も好きなのでかまわない。 席に着き、ホットコーヒーを注文すると、声をかけてきたその女性がうやうやしく運んできてくれた。しかも、カップを置くと空いていた隣の席に腰をおろし、あれこれわたしに話しかけてくる。 「どこから来たの? ダナン? 違う違うお国の話よ。日本? いいわねぇ、わたしも行ってみたいわ」 興味津々でたずねてくる彼女。ひょっとするとこの彼女がわたしのフランチェスカなのだろうか。 「帰りにまた寄ってね」 フランチェスカAの声にうなずきながら、わたしはエンジンをスタートさせた。ババババッと調子だけはいいがパワーのまるで感じられない音がホイアンの港に響き渡り、バイクは発進した。 実際にこの目で見るホイアン郡の橋は、想像していたよりもかなり小さかった。全長は5メートルほどだろうか。小さいうえに古く、なんだか薄黒く汚れている。 考えていてもしかたないので、とりあえず写真を撮ることにした。 そんなこともあって、どこかで見ているかもしれないフランチェスカの視線を意識しながら、わざとらしく何度もレンズを交換して写真を撮ってみる。 適当に写真を撮ってバイクにまたがる。フランチェスカBこと行商のバアさんは、まだわたしを見つめている。 帰ろうかダナンへ。
|
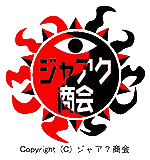
 ジャアク商会と藤井伸二への声援、激励、連絡、お仕事のご依頼はこちらへ ジャアク商会と藤井伸二への声援、激励、連絡、お仕事のご依頼はこちらへ |