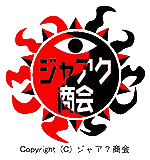|
戦後の復興機運と共に明るくなりかけていたタイ国の雰囲気に水を差す不幸な事故の後に即位されたのは、ラーマ8世の弟であり、これまで一緒にスイスで教育を受けておられたプーミポン・アデュンヤデーッ王子であった。
 ラーマ9世ことプーミポン・アデュンヤデーッ現国王は、タイ王国がまだシャム王国と呼ばれていたころの1927年12月5日、シャム国内ではなくアメリカはマサチューセッツ州ケンブリッジにおいて、ソンクラーのマヒドン王子の次男としてお生まれになった。 ラーマ9世ことプーミポン・アデュンヤデーッ現国王は、タイ王国がまだシャム王国と呼ばれていたころの1927年12月5日、シャム国内ではなくアメリカはマサチューセッツ州ケンブリッジにおいて、ソンクラーのマヒドン王子の次男としてお生まれになった。
血縁的にはラーマ5世の孫にあたり、当時のシャム国を治めていたラーマ7世とは腹違いの甥にあたる。そして、この時はまだ国王としての地位が約束されていたわけではなかった。
戦争が終わり、国王としてラーマ8世がタイに戻る日がやってきた。弟であるプーミポン王子も、仲良く兄と戻ってきて、タイの土を踏んだ。この瞬間も、まだ彼は、王の弟であった。
しかし、帰国して間もない1946年6月10日に発生した悲劇によって兄が崩御。そしてその12時間後、電撃的に弟プーミポン・アデュンヤデーッ王子が後継者となった。
ここに、ラーマ9世の歴史が始まる。
 しかし、この新国王も、即位当時は19歳で、学業を最後まで終えておらず、王位を継いだものの、ふたたびスイスへ戻ってしまった。 しかし、この新国王も、即位当時は19歳で、学業を最後まで終えておらず、王位を継いだものの、ふたたびスイスへ戻ってしまった。
タイに国王のいない時代が終わったのは1950年のこと。同年4月28日、フランス大使兼陸軍大将の娘であり、ラーマ5世からの遠い親戚にあたる17歳のモン・ラーチャウォン・シリキット嬢と長い交際の末華々しく結婚。
さらに、その5日後の5月5日、正式に王位を継承したことを示す盛大な式典を行い、ここに完全なチャクリー王朝第9番目の国王が誕生した。
プーミポン国王は、活動的だ。
農作物の研究を続け、王宮内に研究用の牧場と農園を持ち(自前のブランドを持っている)、ヨットを作ってレースに出場し(東南アジア大会で優勝)、楽器を操って作曲をし(ブロードウエイのミュージカルにも使われた)、どこへ行くにもキャノンの一眼レフを離さず(写真集も出版されている)、油絵を描き(国立美術館に飾られている)、映画も作るといった多彩な趣味を発揮。
どうも、もともと学者肌、芸術家肌であったらしく、スイスでのアカデミックな生活態度を今も続けておられるようだ。
このうえ、ひんぱんな王室行事には欠かさず立ち会っており、その多忙ぶりは一国の国王らしからぬものがある。
 王室主催のヨットレースも毎年開催されるが、国王といえども楽に勝たせてもらえないところがおもしろい。 王室主催のヨットレースも毎年開催されるが、国王といえども楽に勝たせてもらえないところがおもしろい。
写真も雑誌に毎月投稿されているらしいが、謝礼は一般投稿家と同じで数十年間据え置きとか。
神経質で気難しそうな顔付きをされているが、発言はタイ人らしいユーモアに満ちていて格式ばるばかりではない。
誰からも愛されているのは、そういった理由もあるのだろう。
そんな国王を襲った最大の不幸は 「ウボンラット王女の結婚」 だろうか。
国王は通例にならって若い王女をアメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)に留学させ、原子核物理学を学ばせていたのだが、王女は家族の承諾なしに、21歳でアメリカ人ピーター・ジェンセン氏と電撃結婚。そのまま現地で新婚生活を始めてしまったのだ。
最愛の娘に裏切られた国王は怒り爆発。かわいさ余って憎さ百倍とばかりに親子の縁を切ってしまい、ウボン王女は王族としての権利と地位を剥奪されてしまう。
 こういった王族の駆け落ち騒ぎは長いチャクリー王朝の歴史の中でも何度か起こっているのだが、以後、国王はすっかり懲りてしまい、長男ワチラロンコーン王子と次女シリントーン、三女チュラボーン両王女には海外留学を認めず、タイ国内で教育を受けさせるようにした。 こういった王族の駆け落ち騒ぎは長いチャクリー王朝の歴史の中でも何度か起こっているのだが、以後、国王はすっかり懲りてしまい、長男ワチラロンコーン王子と次女シリントーン、三女チュラボーン両王女には海外留学を認めず、タイ国内で教育を受けさせるようにした。
しかし、不幸な時代もいつかは終わる。劇的な離縁騒ぎは事件から8年後の1980年8月、ウボン元王女の突然の帰国によって決着した。
二人は王宮内において全面的に和解、王族への復帰も認められ、8年ぶりに一家に笑顔が戻った。
ウボン元王女は現在離婚しているが、三人の子供にはそれぞれプロイパイリン、ブーミ、シリキティヤと、両親にちなんだ名前がつけられている。
 国王の子供たち(といってもみなさん大人だが)で、現在唯一の独身は、次女シリントーン王女。兄、姉、妹はすでにご結婚され子供もいるが、王女は婚期が遅れ気味。 国王の子供たち(といってもみなさん大人だが)で、現在唯一の独身は、次女シリントーン王女。兄、姉、妹はすでにご結婚され子供もいるが、王女は婚期が遅れ気味。
国王に勝るとも劣らない活発な御活動が原因なら、ちょっと気の毒。
才女として知られ、著作もいくつか出版されている。大の親日家らしいので、わたしたち日本国民も目が離せない。
今では名君チュラロンコーン・ラーマ5世に匹敵する名君と謳われているプーミポン・ラーマ9世は、1970年代に起こった学生による改憲運動や近隣諸国の共産化による国家的危機を乗り越え、200年間続いてきたチャクリー王朝にかつての栄光と威厳と取り戻した。
一時は王制の危機も囁かれていたが、クーデターを成功させるため政治家たちに王制が利用されたことと、プーミポン王の英知・機知・人格によって、現在の絶対とも言える権威を築きあげた。 |
 ラーマ9世ことプーミポン・アデュンヤデーッ現国王は、タイ王国がまだシャム王国と呼ばれていたころの1927年12月5日、シャム国内ではなくアメリカはマサチューセッツ州ケンブリッジにおいて、ソンクラーのマヒドン王子の次男としてお生まれになった。
ラーマ9世ことプーミポン・アデュンヤデーッ現国王は、タイ王国がまだシャム王国と呼ばれていたころの1927年12月5日、シャム国内ではなくアメリカはマサチューセッツ州ケンブリッジにおいて、ソンクラーのマヒドン王子の次男としてお生まれになった。 しかし、この新国王も、即位当時は19歳で、学業を最後まで終えておらず、王位を継いだものの、ふたたびスイスへ戻ってしまった。
しかし、この新国王も、即位当時は19歳で、学業を最後まで終えておらず、王位を継いだものの、ふたたびスイスへ戻ってしまった。 王室主催のヨットレースも毎年開催されるが、国王といえども楽に勝たせてもらえないところがおもしろい。
王室主催のヨットレースも毎年開催されるが、国王といえども楽に勝たせてもらえないところがおもしろい。 こういった王族の駆け落ち騒ぎは長いチャクリー王朝の歴史の中でも何度か起こっているのだが、以後、国王はすっかり懲りてしまい、長男ワチラロンコーン王子と次女シリントーン、三女チュラボーン両王女には海外留学を認めず、タイ国内で教育を受けさせるようにした。
こういった王族の駆け落ち騒ぎは長いチャクリー王朝の歴史の中でも何度か起こっているのだが、以後、国王はすっかり懲りてしまい、長男ワチラロンコーン王子と次女シリントーン、三女チュラボーン両王女には海外留学を認めず、タイ国内で教育を受けさせるようにした。 国王の子供たち(といってもみなさん大人だが)で、現在唯一の独身は、次女シリントーン王女。兄、姉、妹はすでにご結婚され子供もいるが、王女は婚期が遅れ気味。
国王の子供たち(といってもみなさん大人だが)で、現在唯一の独身は、次女シリントーン王女。兄、姉、妹はすでにご結婚され子供もいるが、王女は婚期が遅れ気味。