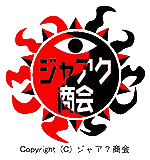|
私は今、ベトナムのホーチミン市のとある小さな日本の会社で仕事をしている。多くの弱小企業がそうであるように、この会社もまた 「なんでもやりまっせ」 という姿勢で世の荒波をくぐり抜けているので、仕事の分野は多肢にわたる。
一応、コンサルティング、コーディネーション、リサーチと名刺に擦り込んであるものの、本来はその後に 「万相談事」 とでも書かれていなければウソというものだ。
次々と刺激のある新しい仕事に取り組めて、やりがいがあります……と言えば言えなくもないが、早い話がその日暮らしで精いっぱいということなのだ。
こんな生活をする前、1991年10月にベトナムに来た当時私は日本語教師だった。ホンの小遣い程度の金をもらい、1年半日本語を教えた。その後、なんとなくもう少しベトナムにいてみようかなどという実に軽佻浮薄な動機で、たまのアルバイトで糊口をしのぎつつブラブラしていた。ある日ふと気づくと、コンピューターの前で仕事をする現在の私がいた、と言うわけだ。
そんな私の日常を破るように、いつもは静かな事務所の電話がなったところから、この物語は始まる。1996年の雨期真っ盛りの朝であった。
「ベトナムと中国を結ぶ鉄道が開通したそうですが、列車でベトナムのハイフォンから中国の昆明まで旅をして、両国を紹介するテレビ番組を作りたい。ついては、ベトナムサイドのコーディネーションをお願いできるでしょうか」
日本のあるプロダクションの若手ディレクターは少しかん高い声で、ゆっくりとそんなようなことを言った。
私はもちろん 「できますできます」 と答えた。頭の中ではが点滅していた。
ここで話は11月にとぶ。その間の事務手続きなどに読者をつきあわせては申し訳ないからだ。
ただ、ひとつ覚えておいてほしいのは、番組ができたばかりの衛星放送向けのものであったため、超のつく低予算で作らなければならなかったことだ。
ロケハンのため一足先にハノイ入りしたディレクターと合流するため、カメラクルーやベトナム外務省プレスセンターのインスぺクターと共に、早朝便でハノイに向かった。ベトナムでは、取材班単独での撮影は許可されていない。必ずプレスセンターから 「お目付け役」 が来て、行動を共にする。彼が不向きと判断したものは、撮影することができないわけだ。
しかし、許可、根回し、現場でのトラブル処理から通訳までやってくれるのでたいへん助かるという面もある。
打ち合わせ後、ハノイ駅から列車で、旅のスタート地点ハイフォンに向かう。車を雇えない我々は、撮影機材や個人装備を自分達で列車内に引き上げなければならない。ジュラルミンケースに入った諸々の撮影機材は日頃箸以外ものを持たない私にとってとにかくひたすら重い。
列車内での撮影、インタビューを終え、ホテルに着き、すぐに夜の街の撮影に繰り出した。
ハイフォンはベトナム一の港町で、北部海上輸送の要だ。郊外に大きな工業団地も建設され、北部コンビナートの中心地となる日も近い。周辺にはカジノとリゾートビーチの街ドーソン、海の桂林ハロン湾など観光名所も多い。
しかし、観光地まで足を延ばしている時間も予算も我々にはない。翌日の午前中、すばやく港や市場でカメラを回し、ハノイへ向かう列車に乗り込んだ。
ハノイのホテルでトラブル発生。
1カ月以上前にシングル5部屋を3日間予約したのだが、今日のみ3部屋しかないという。安ホテルならではの悲劇である。
じゃあ他のホテルに、と言えるほどハノイのホテル事情は良くない。30ドル程度の部屋が5部屋すぐに見つかるのは奇跡に等しいのだ。
と言って3部屋が5部屋に増えるわけもない。そこで、ディスカウントの交渉となった。半額(3日分トータルの)又は最高級ホテルの部屋を取れ! がこちらの言い分。かなり無理があるのは承知の上だ。ホテル側は、今日の分の30%引、ギャップは大きい。
なだめ、脅し、泣きつき、1時間を超える交渉の結果、3日分トータルの35%引きで交渉成立。皆に納得してもらって、1晩だけ2部屋をツインユーズにした。
毎日、朝早くから夜遅くまで走り回って、とにかくハノイでの撮影を終えた。明日はいよいよ中越国境の街ラオカイに出発だ。
4時起床、5時10分発の列車にかけ込む。駅の入り口でリヤカーを雇って、100mほど先の列車まで荷物を運ぶ。
出発風景を撮影し落ち着いた頃、夜が明け始めた。列車には寝台車が連結されているが、夜行ではないので切符は売ってくれない。とはいっても行き来はできるので、車掌の諒解を取ってコンパートメントをひとつ借り、交代で仮眠する。
座席は荷物置き場となり、買い込んでおいた食料を広げて食堂にもなった。列車全域が仕事場で、職住接近の基本スタイルが確立されたわけだ。これから12時間近い時間を我々はこの臨時オフィスで過ごすことになる。
いくつもの駅に停まり、停まるたびに乗客が増えていく。ある駅でどっと乗り込んできた乗客に我々の臨時ホテルはついに占領され、食堂オフィスへの撤退を余儀なくされた。
長い午後の強い日射しが、小高い丘の連なりと緑の田園、小さくかたまった集落に照りつける物憂い午後がオフィスの窓外に広がっている。
そんな中を列車はひたすらラオカイの街を目指して走る。ラオカイから先中国まで線路はずっと繋がっていて、貨物の行き来はあるのだが、まだ旅客列車は乗り入れてはいない。だから中国へ行く人々はいったんラオカイで列車を降り、歩いて国境を越え、再び中国側で列車に乗り込むことになる。
南国の太陽にようやくパワーダウンが見え始めた午後4時すぎ、窓の外にラオカイの街が見え始めた。
翌日、国境と中越貿易をしている会社を取材した後、山あいの街サパに向かう。サパは週末に少数民族が集まって市を開き、夜は歌垣があることで有名な避暑地だ。
車は勾配のある山道をのぼっていく。モン族やザオ族の独特の民族衣装が目につきだす。やがて棚田が目立ち始め、空気がヒンやりとしてきたら、サパは目の前だ。
サパはホテルやゲストハウス、みやげ物屋、レストランが建ち並ぶ小さな街だ。中心は仮設市場で、3m幅の小道に小さな店が軒を並べ、観光客と少数民族があふれている。少数民族は12、3才の少女たちを含め、圧倒的に女性が多い。
背中の篭に民芸品や楽器、指輪や腕輪などの金属加工品、独特の模様で染められたり、刺繍されたりしている布などを容れ売り歩いているのはモン族。赤い大きな座布団状の帽子を被り、派手な腰飾りをつけたザオ族、道端に店を広げて染料を売るタイ族、とにかくきれいな衣装が目立つモン・ホア族など、土曜日には5〜6種類の民族が周辺の村から歩いて集まってくる。
そんな週末の夜、すべての観光客がぜひ見たいと思っているのが、ザオ族の歌垣だ。男と女が掛け合いで即興歌を唄い、気が合えば手に手を取って闇に消えていくという、なんともうらやましい習慣である。
残念ながら、ザオ族以外は参加できないため、我々は指をくわえて見物するしかない。
しかし、なんということだ! 歌わないのである。
そりゃぁ公衆の面前で愛を確認するのが恥ずかしいのは良くわかる。だからといって、隅の暗がりであらかじめ吹き込んでおいたカセットテープを聴き合うというのはどういうものか。文化の喪失を憂いる観光客をしりめに、1〜2のグループが、カセットテープを聴くだけなのだ。
観光客はあきらめても、テレビ屋はあきらめない。暗がりのグループに近づいて、交渉が開始された。ヤラセなどと言わないでほしい。残り少ない貴重な文化を後世に残す大事業なのだ、と理解していただきたい。
やがて1曲3ドルほどで交渉が成立し、場所も近くの林に移して、木立越しに見つめ合う目と目、切々たる愛を込めて男は唄い、女も歌を返し、二人は何処へともなく去っていく、というような場面が撮影された。
カメラの後ろを十重二十重に人が囲み、私は 「静かに!フラッシュは焚かないで!」 と注意して回りながら、 “今度来たときは、「ザオ歌垣シアター」 なんて言うものができてたりして” という思いが頭から離れなかった。
翌日。午前中、一番近いモン族の村に行く。
道が悪く、車で行けないため、カメラやバッテリー、三脚などを担いで山道を40分ほど歩く。しかし、汗だくになって歩いたわりにあまりいい絵が撮れなかった。ディレクターは、
「豚を殺して料理してるところなんか生活感があっていいのですが。そんなとこ取れませんかねぇ」
などと言う。
じつは、だいぶ前から彼はそれを口にしていたのだが、彼以外のメンバーの間で、その話題には触れないと言う暗黙の了解ができていたのだ。
皆が黙っていると、彼は、
「豚殺すところがあればこの番組は大成功なんだがなぁ」
と言うトドメの言葉を、小さくもハッキリ、キッパリとつぶやいた。
我々は豚屠殺現場を求めて、午後、車で入れるという16km離れた村に向かった。
ところが……あと6kmというあたりでドライバーが突然車を止め、前方を見つめ、
「この先はちょっとキビシイもんね」
と言うではないか。
たしかに凹凸が目立ち始め、こぶし大の石も転がっている。しかたなく一行は、またも “歩け行軍” 状態に突入した。
道はその先しばらくは悪かったが、やがて持ち直した。しかしずーっとどこまでも登りである。
山の上にたつ古い教会を目指して、ただモクモクと歩く。が、教会はなかなか近づかない。途中で捕まえたバイクタクシーで荷物を運び、身軽になった一行はなんとか教会までたどり着いた。
教会を撮影し、茶店で一息入れて、「村はどこか」 とたずねれば、答えは非情にも、
「5km先だよ」
みな疲れ果てている。5kmは厳しい。それに日暮れが近く、早くしないと撮影ができなくなる。
その時、濃厚になってきた “豚はあきらめだ” という雰囲気を破るように、
「とにかく行きましょう」
とディレクターが言った。一同は無言で腰を上げ、歩き始めた。
5分も歩いたろうか。先頭を行くインスぺクターが向こうから来たモン族の男となにやら話し始めた。
「村までは1時間半かかる。豚なら家で飼っているから、家に来ればいい。今夜は日本からのお客さんを交えて宴会としようではないか」
男はそんなようなことを言っているらしい。
ディレクターが即決し、彼の家へ向かった。残念ながら宴会はご辞退申し上げ、料理をするところを撮影したら帰らざるをえない。豚は彼らの貴重な財産なので、ちょっと高めのオファーをされたが、もちろん値切ったりしない。
男の家は、わき道を入って小さな川を越えた先だった。
家族に紹介されたあと、早速撮影開始だ。
男が包丁を研ぐ。豚が小屋から引きずり出される。豚の悲鳴が辺りに響きわたる。私は興味津々で見つめていた。
しかし、ディレクターに、
「車のところまでもどって、なんとか100mでもいいからこっちに来てくれるように頼んでくれませんか」
と言われ、千載一隅の豚屠殺現場を目撃するチャンスを逸したのだ。
翌朝、ラオカイの街に戻った。
イミグレーションの撮影をし、クルーは中国へと国境の橋を越えた。
私とプレスセンターのインスぺクターはこれから列車で12時間かけてハノイへ戻り、撮影ずみテープの検閲を受けなければならない。
DHLでテープを日本に送るまで、私に安らぎの時は来ない |