|
仏教は、紀元前588年の12月8日、釈迦族出身のシッタールダ王子が苦行の末に悟りを開き、仏陀となった日から始まった。仏陀はそれ以後の生涯を布教と啓蒙活動に捧げ、地方を旅して教義を説き、80歳で入滅された。 もう一方の保守正統派は、あくまでも仏陀本来の教えにこだわり、厳しい修行と禁欲によって選りすぐられた者だけに救済の道が開かれることから 「上座部仏教」 と呼ばれるようになった。 |
|
仏教は、紀元前588年の12月8日、釈迦族出身のシッタールダ王子が苦行の末に悟りを開き、仏陀となった日から始まった。仏陀はそれ以後の生涯を布教と啓蒙活動に捧げ、地方を旅して教義を説き、80歳で入滅された。 もう一方の保守正統派は、あくまでも仏陀本来の教えにこだわり、厳しい修行と禁欲によって選りすぐられた者だけに救済の道が開かれることから 「上座部仏教」 と呼ばれるようになった。 |
|
|
|
この一派は、俗に 「小乗仏教」 と呼ばれているが、これは 「(大乗に対して)劣っている乗り物」 という意味で使われる大乗側からの一方的な蔑称である。つまり、ひとりしか乗ることができないという意味で、その狭量さを軽蔑しているのだ。 1950年の世界仏教徒会議でこの名称の正式撤廃が決議されたが、調べていくとこの 「ひとり乗り」 という言い方が、意外と上座部仏教の本質を表している。 上座部仏教徒の最終目標は、仏陀(個人名ではなく、悟りを得て涅槃に入った人を指す)の域に達することである。 の四戒は、絶対に犯すべからざるものとされている。 を加えた五戒を守るべくよう義務づけられている。
このように厳格な戒律を守り通し、厳しい修行を経たものだけに救いのあるのが上座部仏教であり、黙っていても誰かが救ってくれる大乗仏教とは大きな違いがある。 |
|
|
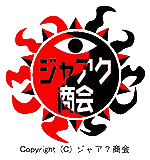
 ジャアク商会への声援、激励、連絡はこちらへ ジャアク商会への声援、激励、連絡はこちらへ |