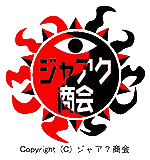仏塔
チェディ、プラーン。英語ではパゴダ、ストューパ。
日本語ではストゥーパ転じて卒塔婆。
タイの寺院には仏塔を建てるのが通例となっている。仏塔のない寺院は珍しいと言っていいし、ない場合はその目的を肩代わりするものが建てられているのが一般的だ。
仏塔は本来、仏舎利(ブッダの遺骨)を納めるために作られたものだが、のちに重要な仏法に関するものを祭る建築物へと性格を変えていった。習慣的に墓を持たないタイの人たちは、葬儀後遺体を焼却し、遺骨をこの中に納めてもらって儀式の完成とする。仏塔はタイ人にとって卒塔婆の意味を持っていると考えていいだろう(語源的には同じもの)。
 仏塔には円錐型をしたチェディと呼ばれるものと、ラテライトを使いトウモロコシのような形に築き上げたプラーンと呼ばれるものの2種類があり、年式や建築当時の流行などによりいくつかの様式がある。 仏塔には円錐型をしたチェディと呼ばれるものと、ラテライトを使いトウモロコシのような形に築き上げたプラーンと呼ばれるものの2種類があり、年式や建築当時の流行などによりいくつかの様式がある。
北部・東北部・南部タイの寺院ではタートと呼ばれる平面を多用した非円錐型の仏塔をよく見かけるが、バンコク市内では一般的ではない。
チェディは大まかに3つの建築様式に区別されている。
チェディの語義は「記念すべき場所」で、完全な釣鐘型の円錐をしているのがスリランカ型チェディ。上座部仏教の基礎を築いたスリランカから伝来した正当派チェディだ。
ワット・プラケオのプラ・シー・ラッタナー・チェディなどはこの典型で、内部には本当に釈迦の遺骨が納められている。
もうひとつのチェディは、釣鐘という基本形は変わらないものの、台座が多角形をしているのが特徴。これはスリランカ様式とは違い、タイで若干の仕様変更を受けたものだ。
教えは受け継いでいるものの寺院の建築様式がスリランカのものとは細部で違っていることが多く、スリランカの正統上座部信仰者にしてみれば邪道ということになるらしいが、ところ変われば様式も変わる。
もっとも変わってしまったのは面と直線を基調とした細長い中小型チェディだが、こちらはタイ国において独自に開発されたものらしい。
チェディはいくつもの段を重ねて作り上げられた複雑な復層構造をとっているが、これも装飾のため無意味に積み上げられているのではない。この一段一段、角の数や積み重ね方のすべてに可能な限りの仏教的意味合いが込められている。
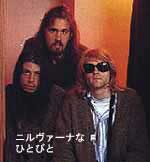 おもに仏教世界とその教えを表現しているのだが、すべて理解するには仏教学をひととおり学んでおく必要があるだろう。 おもに仏教世界とその教えを表現しているのだが、すべて理解するには仏教学をひととおり学んでおく必要があるだろう。
簡単に説明すると、仏塔の頂点は仏教の最高到達点である涅槃(ニルヴァーナ)を表している。以下、区切りや段差ごとに仏教一般についての説明があり、最下段の台座はわたしたちが住んでいる世界全体を示している。チェディには仏教のすべてが具現化されているのだ。
仏塔のもうひとつの流れであるプラーンは、ヒンズー/バラモン教寺院には欠かせない建築様式のひとつである。
タイでプラーンと言えば純粋に「塔」をさすが、これはそもそもバラモン寺院の神殿のことを指していた。
代表的寺院であるワット・アルンを見てもらえばわかるとおり、プラーンを持つ寺院はどこか仏教的ではない雰囲気を持っている。塔の先端部に飾られている避雷針のようなものは、バラモン3大神のひとりシヴァ神のシンボルであるノッパスーンだし、中腹にはインドラ神やその乗り物であるエラワン象が意匠として彫り込まれていることもある。
この中に仏舎利が納められるのは奇妙な話だが、タイ仏教におけるバラモン教の位置付けを知る好例でもある。 |
 仏塔には円錐型をしたチェディと呼ばれるものと、ラテライトを使いトウモロコシのような形に築き上げたプラーンと呼ばれるものの2種類があり、年式や建築当時の流行などによりいくつかの様式がある。
仏塔には円錐型をしたチェディと呼ばれるものと、ラテライトを使いトウモロコシのような形に築き上げたプラーンと呼ばれるものの2種類があり、年式や建築当時の流行などによりいくつかの様式がある。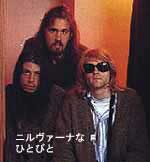 おもに仏教世界とその教えを表現しているのだが、すべて理解するには仏教学をひととおり学んでおく必要があるだろう。
おもに仏教世界とその教えを表現しているのだが、すべて理解するには仏教学をひととおり学んでおく必要があるだろう。